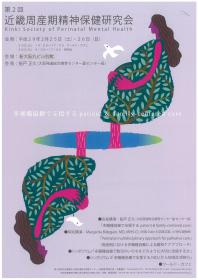- ホーム
- 協会からのお知らせ
協会からのお知らせ
2017/4/3
2017/3/13
2016年度・第10回公開講座が「看取りのケアを考える〜ケアの道しるべと私たちの心得」のテーマで開催されました。

3月12日(日)当協会で、第10回公開講座を実施しました。
講師は池永昌之先生です。
池永先生は淀川キリスト教病院緩和医療内科主任部長してご活躍されています。
受講生のご感想をご紹介します。
○看取りの時の家族への声かけの仕方など、今までこれだけ具体的に講義を受けたのは初めてでとてもわかりやすかったのと、自分の今のやり方の振り返りができました。現在、ケアにあたっている利用者への対応を今までと違う気持ちで見つめかかわっていけると思いました。とてもいい講義で、先生が同じ目線でお話くださっていたので心で感じる事が多かったです。私が知りたかったことがたくさん聞けました。
また参加しようと思います。ありがとうございました。
○看取りのケアに大切な考え方がよくわかりました。医師とご家族の定期面談を始めたところですが、ご本人の一番側にいる看護者とご家族が、ご本人についてゆっくり話できる場を作っていきたい。今回、上司のすすめで参加しましたが、グリーフケアというものを理解できていませんでした。もっと、グリーフケアについての講習会に参加していきたいです。
○今春から働いている病院で発足するグリーフケアチームの一員として、患者さんや家族に対してどのようなケアが求められているのか、目に見えないスピリチュアルな部分のお話をたくさん聞くことができました。亡くなられた患者さんのケアばかりに目を向けてしまっていて、周りの方々への声かけが十分できていなかったと反省しました。今後のケアに活かしていきたいと思います。
○外来、訪問の患者さんで直面している問題にあてはまることもあり(推定意思の決定)職場へ持ち帰ってDr、Ns と相談する材料にできると思えました。講義の内容の一部はすぐに活用したいと思います。外来勤務ではカンファレンスを持つ時間も少ないですが、できるだけみんなに資料を見てもらった上で、多くの人と話せる機会を作りたいです。
お越しいただいた皆様、池永先生ありがとうございました。

3月12日(日)当協会で、第10回公開講座を実施しました。
講師は池永昌之先生です。
池永先生は淀川キリスト教病院緩和医療内科主任部長してご活躍されています。
受講生のご感想をご紹介します。
○看取りの時の家族への声かけの仕方など、今までこれだけ具体的に講義を受けたのは初めてでとてもわかりやすかったのと、自分の今のやり方の振り返りができました。現在、ケアにあたっている利用者への対応を今までと違う気持ちで見つめかかわっていけると思いました。とてもいい講義で、先生が同じ目線でお話くださっていたので心で感じる事が多かったです。私が知りたかったことがたくさん聞けました。
また参加しようと思います。ありがとうございました。
○看取りのケアに大切な考え方がよくわかりました。医師とご家族の定期面談を始めたところですが、ご本人の一番側にいる看護者とご家族が、ご本人についてゆっくり話できる場を作っていきたい。今回、上司のすすめで参加しましたが、グリーフケアというものを理解できていませんでした。もっと、グリーフケアについての講習会に参加していきたいです。
○今春から働いている病院で発足するグリーフケアチームの一員として、患者さんや家族に対してどのようなケアが求められているのか、目に見えないスピリチュアルな部分のお話をたくさん聞くことができました。亡くなられた患者さんのケアばかりに目を向けてしまっていて、周りの方々への声かけが十分できていなかったと反省しました。今後のケアに活かしていきたいと思います。
○外来、訪問の患者さんで直面している問題にあてはまることもあり(推定意思の決定)職場へ持ち帰ってDr、Ns と相談する材料にできると思えました。講義の内容の一部はすぐに活用したいと思います。外来勤務ではカンファレンスを持つ時間も少ないですが、できるだけみんなに資料を見てもらった上で、多くの人と話せる機会を作りたいです。
お越しいただいた皆様、池永先生ありがとうございました。
2017/3/7
2016年度・第3回公開セミナーが「グリーフケア:遺族、そして看護師自身のために」のテーマで開催されました。

3月4日(土)知恩院和順会館で、第3回公開セミナーを実施しました。
講師は広瀬寛子先生です。
広瀬先生は戸田中央総合病院カウンセリング室室長として活躍されています。
緩和ケアにおけるグリーフケア(患者・家族・遺族・看護師を対象としたカウンセリングとサポートグループ)に力を注がれています。
当日は、サポートグループの運営の実際と、看護師自身のグリーフケアについてお話いただきました。
講義だけでなく、受講者のお話を聞くスタイルで進められていました。
受講生のご感想をご紹介します。
○私は患者、家族と話をしていてよく泣けてきました。そのたび「いけない」と思い、我慢してきました。以前、看護部長からも患者の前では泣いてはダメと言われたこともありましたが、今日いいんだと思えて楽になりました。サポートグループも行っているので、今回の資料を持ち帰り話します。遺族との関わり方、話し方がわかりました。ありがとうございました。
○グリーフケアは遺族に対するケアだと思っていたが、ガンを告知された方や障がいをもつ子どもの家族にもグリーフケアが大切だということを学んだ。自分がしている訪問看護に自信がなかったが講義を受けて自信が持てたことはとてもよかったです。
○悲嘆を受け止め、適応していくにはステップが必要ということがわかった。また、看護師として色んな感情を持っていいということと、感情を置いておくというセルフコントロールをするための考え方を教わったと思います。
○遺族の方が悲嘆に適応していく過程は、その人が歩んでいく道であり、医療者はそれを見守る場と空気になれればよいことを改めて学ばせていただきました。看護師自身のグリーフケアに関しては、今まで辛かった体験や振り返りきれていなかったことなどを色々と思いだしつつ、自分から発信していくことの大切さを感じました。
○昨年、流産・死産・新生児死を経験された方の遺族会を立ち上げた。会の方向性を確認できた。一緒に行っているスタッフに伝えたい。すぐに活用できる内容であった。
お越しいただいた皆様、広瀬先生ありがとうございました。

3月4日(土)知恩院和順会館で、第3回公開セミナーを実施しました。
講師は広瀬寛子先生です。
広瀬先生は戸田中央総合病院カウンセリング室室長として活躍されています。
緩和ケアにおけるグリーフケア(患者・家族・遺族・看護師を対象としたカウンセリングとサポートグループ)に力を注がれています。
当日は、サポートグループの運営の実際と、看護師自身のグリーフケアについてお話いただきました。
講義だけでなく、受講者のお話を聞くスタイルで進められていました。
受講生のご感想をご紹介します。
○私は患者、家族と話をしていてよく泣けてきました。そのたび「いけない」と思い、我慢してきました。以前、看護部長からも患者の前では泣いてはダメと言われたこともありましたが、今日いいんだと思えて楽になりました。サポートグループも行っているので、今回の資料を持ち帰り話します。遺族との関わり方、話し方がわかりました。ありがとうございました。
○グリーフケアは遺族に対するケアだと思っていたが、ガンを告知された方や障がいをもつ子どもの家族にもグリーフケアが大切だということを学んだ。自分がしている訪問看護に自信がなかったが講義を受けて自信が持てたことはとてもよかったです。
○悲嘆を受け止め、適応していくにはステップが必要ということがわかった。また、看護師として色んな感情を持っていいということと、感情を置いておくというセルフコントロールをするための考え方を教わったと思います。
○遺族の方が悲嘆に適応していく過程は、その人が歩んでいく道であり、医療者はそれを見守る場と空気になれればよいことを改めて学ばせていただきました。看護師自身のグリーフケアに関しては、今まで辛かった体験や振り返りきれていなかったことなどを色々と思いだしつつ、自分から発信していくことの大切さを感じました。
○昨年、流産・死産・新生児死を経験された方の遺族会を立ち上げた。会の方向性を確認できた。一緒に行っているスタッフに伝えたい。すぐに活用できる内容であった。
お越しいただいた皆様、広瀬先生ありがとうございました。
2017/3/3
2017年度(前期)グリーフケアスクール/2017年度(通年)公開講座・公開セミナーのスケジュールを公開しました。

この度、2017年度前期(4月〜9月)のグリーフケアスクール看護師・助産師コース、介護・福祉従事者コースと、2017年度公開講座・公開セミナーのスケジュールを公開しました。
看護師向けの講座では、新たに以下の2名の講師にご支援いただけることとなりました。
医療現場において、子供に対するグリーフケアは重要だと認識され、患者ケアにもつながると考えられています。
一方で、子供がどの程度、死を理解しているかがわからず、実践が難しいと感じることも多いです。
そこで、「親を亡くした子供に対するグリーフケア」をテーマに研究されている方々2名に、公開講座・公開セミナーでご登壇いただきます。
・小島ひで子先生
小島ひで子先生 プロフィール
・茎津智子先生
茎津智子先生 プロフィール
また、今までの講師各位にも引き続きご支援いただき、皆様が働かれている領域やご関心に併せて講座を設けています。
ご興味のある方はぜひ受講をご検討下さい。
■看護師・助産師コース 基礎級(全6日)
■介護・福祉従事者コース 初級(全2日)
■公開講座・公開セミナー(全1日)

この度、2017年度前期(4月〜9月)のグリーフケアスクール看護師・助産師コース、介護・福祉従事者コースと、2017年度公開講座・公開セミナーのスケジュールを公開しました。
看護師向けの講座では、新たに以下の2名の講師にご支援いただけることとなりました。
医療現場において、子供に対するグリーフケアは重要だと認識され、患者ケアにもつながると考えられています。
一方で、子供がどの程度、死を理解しているかがわからず、実践が難しいと感じることも多いです。
そこで、「親を亡くした子供に対するグリーフケア」をテーマに研究されている方々2名に、公開講座・公開セミナーでご登壇いただきます。
・小島ひで子先生
小島ひで子先生 プロフィール
・茎津智子先生
茎津智子先生 プロフィール
また、今までの講師各位にも引き続きご支援いただき、皆様が働かれている領域やご関心に併せて講座を設けています。
ご興味のある方はぜひ受講をご検討下さい。
■看護師・助産師コース 基礎級(全6日)
■介護・福祉従事者コース 初級(全2日)
■公開講座・公開セミナー(全1日)
2017/2/27
子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座のお知らせ

医療従事者向けグリーフケア講座をご案内致します。
主催はこども遺族の会「小さないのち」です。
当協会開設当初よりご支援いただいている坂下裕子さんが会長をつとめられています。
ご興味のある方は以下、ご参照ください。
●子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座●
グリーフケアを遺族ケアと考える医療従事者が少なくありませんが、小児の家族の多くは、あくまでそれはグリーフケアの一部だと考えます。
そこで「当事者にとってのグリーフケア」とは何かを検討しています。
テーマを変化させながら隔月で実施しておりますので是非お越しくださいませ。
第5回 同じ病気をもって生まれた兄と弟
■内容
心臓に重い病気をもって生まれた長男の闘病と立ち向かい、看取ったのちに、同じ病気をもつ次男の出産に臨み、手術を乗り越えた現在までの体験談です。
「未知の不安」と「再度の恐怖」を、医療スタッフの皆さんにどのように助けられ支えられてきたか、あるいはどんな点に不足を感じたか、など詳細にお伝えします。
長男との頑張りとその死を受け止めるまでを「前編」とし、次の妊娠や出産そして次男との頑張りを「後編」として第5回と第6回の2度に分けてお届けします。
当日は、質疑応答および参加者同士の情報交換を充実させるようにします。
■発表者
「小さないのち」の会員
完全型心内膜床欠損症で長男(0才)を看取り、同じ病気の次男(2才)を育てているお母さんです。
■対象者
医療従事者
■日時
2017年3月12日(日)10:45〜13:00 開場10:30
■場所
関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階
■定員
40人(要予約)
■参加費
小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として
一口500円の寄付を3口(1500円)以上でお願いいたします。
■申し込み・問い合わせ
s-ayumi@pop21.odn.ne.jp
会代表 坂下(さかした) 裕子(ひろこ)
■主催
こども遺族の会「小さないのち」http://www.chiisanainochi.org/
pdf ダウンロード

医療従事者向けグリーフケア講座をご案内致します。
主催はこども遺族の会「小さないのち」です。
当協会開設当初よりご支援いただいている坂下裕子さんが会長をつとめられています。
ご興味のある方は以下、ご参照ください。
●子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座●
グリーフケアを遺族ケアと考える医療従事者が少なくありませんが、小児の家族の多くは、あくまでそれはグリーフケアの一部だと考えます。
そこで「当事者にとってのグリーフケア」とは何かを検討しています。
テーマを変化させながら隔月で実施しておりますので是非お越しくださいませ。
第5回 同じ病気をもって生まれた兄と弟
■内容
心臓に重い病気をもって生まれた長男の闘病と立ち向かい、看取ったのちに、同じ病気をもつ次男の出産に臨み、手術を乗り越えた現在までの体験談です。
「未知の不安」と「再度の恐怖」を、医療スタッフの皆さんにどのように助けられ支えられてきたか、あるいはどんな点に不足を感じたか、など詳細にお伝えします。
長男との頑張りとその死を受け止めるまでを「前編」とし、次の妊娠や出産そして次男との頑張りを「後編」として第5回と第6回の2度に分けてお届けします。
当日は、質疑応答および参加者同士の情報交換を充実させるようにします。
■発表者
「小さないのち」の会員
完全型心内膜床欠損症で長男(0才)を看取り、同じ病気の次男(2才)を育てているお母さんです。
■対象者
医療従事者
■日時
2017年3月12日(日)10:45〜13:00 開場10:30
■場所
関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階
■定員
40人(要予約)
■参加費
小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として
一口500円の寄付を3口(1500円)以上でお願いいたします。
■申し込み・問い合わせ
s-ayumi@pop21.odn.ne.jp
会代表 坂下(さかした) 裕子(ひろこ)
■主催
こども遺族の会「小さないのち」http://www.chiisanainochi.org/
pdf ダウンロード
2017/2/21
京都グリーフケア協会にて2月12日(日)、公開講座が開催されました。

講師は、関西電力病院で緩和医療科部長・心療内科部長(兼務)をされている梶山徹先生です。
テーマは、「スピリチュアルケアとがんの悲嘆ケア」
症例検討やロールプレイなどを交えて行われました。また色々な立場の方が参加され、活気ある講義となりました。
受講生の感想を一部紹介いたします。
●傾聴の意味がわかりました。又自己を振り返ることができました。しっかりお話はお聞きしてますが、いつも「そうかな?」と返答があることに今日、これでは「本当に分かってもらってない」と思われていることに気付きました。その他もスピリチュアルペインは無理にとらなくて良いんだ!!痛みの奥に深いものがあり、希望が見える。目からうろこでした。
●スピリチュアルペインは解決してしまおうという思いが強く、患者さんの話を病気の面から聞いてしまうことが多かったので、解決するのではなく、話を聞く事、患者さんの中に答えがあるので一緒にみつけていこうと思う事ができました。
実際に患者さんとの関わりで活用していきたい。これから患者さんから色々なことを教えてもらっているという感覚を忘れずにしていきたい。
●いつも仕事におわれ、利用者様の話も上の空できいていることも多かったが、会話にもその方のストーリーがあり、全てに意味があり、特にターミナルの方の人生最期に立ち会えることに喜びを感じると考え方を攻めることができた。
今まで、受けたターミナルの講義とは違い、色んな見方ができると思った。
今回、学んだことを実践できるようまとめて日々の仕事に生かしたい。
コミュニケーションの取り方等日頃から練習していきたい。
●色々な疑問を解決できました。
本日の講義で教えて頂いた内容を実際に役立てていきたいと思います。
ご参加頂きました受講生の皆さま、梶山先生、ありがとうございました。

講師は、関西電力病院で緩和医療科部長・心療内科部長(兼務)をされている梶山徹先生です。
テーマは、「スピリチュアルケアとがんの悲嘆ケア」
症例検討やロールプレイなどを交えて行われました。また色々な立場の方が参加され、活気ある講義となりました。
受講生の感想を一部紹介いたします。
●傾聴の意味がわかりました。又自己を振り返ることができました。しっかりお話はお聞きしてますが、いつも「そうかな?」と返答があることに今日、これでは「本当に分かってもらってない」と思われていることに気付きました。その他もスピリチュアルペインは無理にとらなくて良いんだ!!痛みの奥に深いものがあり、希望が見える。目からうろこでした。
●スピリチュアルペインは解決してしまおうという思いが強く、患者さんの話を病気の面から聞いてしまうことが多かったので、解決するのではなく、話を聞く事、患者さんの中に答えがあるので一緒にみつけていこうと思う事ができました。
実際に患者さんとの関わりで活用していきたい。これから患者さんから色々なことを教えてもらっているという感覚を忘れずにしていきたい。
●いつも仕事におわれ、利用者様の話も上の空できいていることも多かったが、会話にもその方のストーリーがあり、全てに意味があり、特にターミナルの方の人生最期に立ち会えることに喜びを感じると考え方を攻めることができた。
今まで、受けたターミナルの講義とは違い、色んな見方ができると思った。
今回、学んだことを実践できるようまとめて日々の仕事に生かしたい。
コミュニケーションの取り方等日頃から練習していきたい。
●色々な疑問を解決できました。
本日の講義で教えて頂いた内容を実際に役立てていきたいと思います。
ご参加頂きました受講生の皆さま、梶山先生、ありがとうございました。
2017/2/10
グリーフケアスクール 介護・福祉従事者コース上級 第4日を実施しました。

講師は、荒牧敦子先生です。
荒牧先生は、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部の代表として、活動されています。
20年間、家族介護者として、認知症・非認知症それぞれを経験されながら義母を老人病院、実父母を在宅で、ご主人を総合病院でそれぞれ看取られました。
本日は、家族介護者当事者としてのご経験からそれぞれをどのように介護し、どのように感じていたかなど、実際の体験を中心にお話いただきました。
認知症の家族介護者が持つ実際の気持ちやおかれた状況を知ることで、普段のケアに役立てていただけたらと考えています。
当協会では、遺族会代表や在宅看取りの経験者、家族介護者の方など当事者の方々にもお話いただいています。
当事者側の視点から学ぶと多くの気づきがあり、ケアの双方向性を考えられるようにしています。
以下、アンケートをご紹介します。
・約20年間の実体験の生の声を聞くことができて、非常に貴重な時間を持つことができました。教科書などではなく、本音の言葉を聞くことができたと感じています。専門用語などないので、リアルにその時の情景が目に浮かぶほど、わかりやすかったです。生の声を介護者にお伝えすることができ、負担や疲れを感じている人の何かのきっかけに繋がればと思います。
・ゆっくりしたテンポで先生の温かな気持ちが伝わる講義でした。質問も十分できました。20年間介護してこられた実体験を元にした講義で、難しい言葉もなく理解できました。グリーフケアの研修に活用するつもりでいる。サ高住のほとんどの方が認知症のため認知所の家族の方の気持ちを知ることは大切だと思う。
・実体験された方の生のお話は、聞いてみないとわからないことがたくさんあり、聞けて良かった。身近に起こる「あるある」ってことの中の、介護者の想いが聞けて良かった。介助の方法、かける言葉で傷つけるなどこれから役立てます。

講師は、荒牧敦子先生です。
荒牧先生は、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部の代表として、活動されています。
20年間、家族介護者として、認知症・非認知症それぞれを経験されながら義母を老人病院、実父母を在宅で、ご主人を総合病院でそれぞれ看取られました。
本日は、家族介護者当事者としてのご経験からそれぞれをどのように介護し、どのように感じていたかなど、実際の体験を中心にお話いただきました。
認知症の家族介護者が持つ実際の気持ちやおかれた状況を知ることで、普段のケアに役立てていただけたらと考えています。
当協会では、遺族会代表や在宅看取りの経験者、家族介護者の方など当事者の方々にもお話いただいています。
当事者側の視点から学ぶと多くの気づきがあり、ケアの双方向性を考えられるようにしています。
以下、アンケートをご紹介します。
・約20年間の実体験の生の声を聞くことができて、非常に貴重な時間を持つことができました。教科書などではなく、本音の言葉を聞くことができたと感じています。専門用語などないので、リアルにその時の情景が目に浮かぶほど、わかりやすかったです。生の声を介護者にお伝えすることができ、負担や疲れを感じている人の何かのきっかけに繋がればと思います。
・ゆっくりしたテンポで先生の温かな気持ちが伝わる講義でした。質問も十分できました。20年間介護してこられた実体験を元にした講義で、難しい言葉もなく理解できました。グリーフケアの研修に活用するつもりでいる。サ高住のほとんどの方が認知症のため認知所の家族の方の気持ちを知ることは大切だと思う。
・実体験された方の生のお話は、聞いてみないとわからないことがたくさんあり、聞けて良かった。身近に起こる「あるある」ってことの中の、介護者の想いが聞けて良かった。介助の方法、かける言葉で傷つけるなどこれから役立てます。
2017/1/30
2016年度・第8回公開講座が「認知症をもちながら老い、逝く高齢者のケア」のテーマで開催されました。

1月29日(日)当協会で、第8回公開講座を実施しました。
講師は中筋美子先生です。中筋先生は兵庫県立大学看護学部で助教として活躍されています。老人看護専門看護師の方です。
特に高齢者看護、特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動と共に、医療機関での実践活動や専門職支援にも取り組まれています。
受講生のご感想をご紹介します。
○生活の質を一番に考えて高齢者に関わる視点を忘れかけていた自分と向き合うことができました。今日見たDVDを活用したいと思います。とても良い環境で学ぶことができました。心が穏やかになれました。ありがとうございました。
○認知症についての知識が深まった。高齢者や認知症についてのガイドライン、映画、本からの引用など知らなかったことを知る事が出来、明日からのケアに活用してきたい。利用者、ご家族にもご紹介したいです。私自身の学びの宝にもなると思います。先生の思いが伝わってきたので感動しました。
○高齢者の受け止め方が変わった気がする。意志決定の支援を充実する必要があると思った。施設内での意志決定支援のために考えている「私のこころづもり」のバックボーンとなる部分を多くもらった。
○認知症を持つ人が体験している世界を改めて感じ、ケアに役立てていきたい。終わり良ければすべて良しと思うようにしてきましたが、それまでの関わり、ケアの過程がとても大事である事、お互いのその人らしさを知れるようにしていきたいと思った。
○認知症のある方に対するケアの考え方を学ぶことができ、認知症の人がしている体験を知ることができました。将来、自分の家族や自分も体験するかもしれないこととして、意思決定などについて話し合っていきたい。もう一度、資料を見直して伝達講習を行おうと思います。
今回も参加いただいた受講生の皆様、中筋先生、ありがとうございました。

1月29日(日)当協会で、第8回公開講座を実施しました。
講師は中筋美子先生です。中筋先生は兵庫県立大学看護学部で助教として活躍されています。老人看護専門看護師の方です。
特に高齢者看護、特に認知症看護を専門として、大学での教育・研究活動と共に、医療機関での実践活動や専門職支援にも取り組まれています。
受講生のご感想をご紹介します。
○生活の質を一番に考えて高齢者に関わる視点を忘れかけていた自分と向き合うことができました。今日見たDVDを活用したいと思います。とても良い環境で学ぶことができました。心が穏やかになれました。ありがとうございました。
○認知症についての知識が深まった。高齢者や認知症についてのガイドライン、映画、本からの引用など知らなかったことを知る事が出来、明日からのケアに活用してきたい。利用者、ご家族にもご紹介したいです。私自身の学びの宝にもなると思います。先生の思いが伝わってきたので感動しました。
○高齢者の受け止め方が変わった気がする。意志決定の支援を充実する必要があると思った。施設内での意志決定支援のために考えている「私のこころづもり」のバックボーンとなる部分を多くもらった。
○認知症を持つ人が体験している世界を改めて感じ、ケアに役立てていきたい。終わり良ければすべて良しと思うようにしてきましたが、それまでの関わり、ケアの過程がとても大事である事、お互いのその人らしさを知れるようにしていきたいと思った。
○認知症のある方に対するケアの考え方を学ぶことができ、認知症の人がしている体験を知ることができました。将来、自分の家族や自分も体験するかもしれないこととして、意思決定などについて話し合っていきたい。もう一度、資料を見直して伝達講習を行おうと思います。
今回も参加いただいた受講生の皆様、中筋先生、ありがとうございました。
2017/1/30
第2回 近畿周産期精神保健研究会のお知らせ

第2回 近畿周産期精神保健研究会が開催されます。
今回は、当協会設立当初より講師としてご支援いただいている、船戸正久先生が会長となります。
領域の方で、ご興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。
【会期】
平成29年2月25日(土) 14:00〜17:00 ワールドカフェ
2月26日(日) 9:00〜17:00 研究会
【会場】
新大阪丸ビル 別館(JR新大阪駅 東口徒歩5分)
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22
【会長】
船戸正久(大阪発達総合療育センター 副センター長)
【会費】
個人5,000円
※ワールドカフェのみの申込み不可
※抄録は当日500円で販売。
※事前申込登録(5,000円)で、参加費・抄録が無料となります。
【申込み先】
第2回研究会事務局 大阪発達総合療育センター 総務課・医局代表:寺裏
TEL 06-6699-8731
FAX 06-6699-8134
Email:teraura@osaka-drc.jp
【会長講演】
座長 窪田昭男(和歌山県立医科大学第2外科学長 特命教授)
「多職種協働で支援するpatient & family-centered care」
【特別講演】
座長 鍋谷まこと(淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院院長)
「Perinatal multidisciplinary for palliative care(周産期における多職種協働による緩和ケアアプローチ)」
Margarita Bidegain MD, MHS-CL (米国Duke大学医学部・小児科准教授)
【シンポジウム】
1、「多職種協働で胎児のいのちをどのように大切に守るか」
Modulator :
和田浩(大阪発達総合療育センター医師)
猿田美雪(淀川キリスト教病院 NICU看護師)
シンポジスト:
宮田郁(大阪医科大学 リエゾン精神看護師)
高橋雄一郎(長良医療センター 産科医師)
武井安津子(愛仁会高槻病院 新生児小児科医師)
佐藤裕美(愛仁会高槻病院 NICU 看護師)
出崎躍(淀川キリスト教病院 臨床心理士)
森喜宣・香奈(大阪医科大学 家族)
柴田兼作(淀川キリスト教病院 家族)
【シンポジウム】
2、「多職種協働で支援するNICUからの地域生活移行」
Modulator :
望月成隆(大阪府立母子保健総合医療センター 新生児科医師)
近藤正子(大阪発達総合療育センター 医療相談室 MSW)
シンポジスト:
祝原賢幸(大阪府立母子保健総合医療センター新生児科医師)
山口真帆(同センター NICU 看護師)
西野千絵(同センター 母性外来看護師)
川野由子(同センター 心理士)
熊清彰(愛染橋病院 小児科医師)
松岡雅一(訪問看護ステーションリハステージ PT)
久保田恵巳(くぼたこどもクリニック 医師)
【ワールドカフェ(事例から学ぶ)】
Facilitator :
杉原康子(大阪発達総合療育センター 臨床心理士)
川野由子(大阪府立母子保健総合医療センター 臨床心理士)
吉田まち子(同センター 看護師)
脇田菜摘(済生会吹田病院 心理士)
出崎躍(淀川キリスト教病院 臨床心理士)
小寺智子(高槻病院 臨床心理士)

第2回 近畿周産期精神保健研究会が開催されます。
今回は、当協会設立当初より講師としてご支援いただいている、船戸正久先生が会長となります。
領域の方で、ご興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。
【会期】
平成29年2月25日(土) 14:00〜17:00 ワールドカフェ
2月26日(日) 9:00〜17:00 研究会
【会場】
新大阪丸ビル 別館(JR新大阪駅 東口徒歩5分)
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22
【会長】
船戸正久(大阪発達総合療育センター 副センター長)
【会費】
個人5,000円
※ワールドカフェのみの申込み不可
※抄録は当日500円で販売。
※事前申込登録(5,000円)で、参加費・抄録が無料となります。
【申込み先】
第2回研究会事務局 大阪発達総合療育センター 総務課・医局代表:寺裏
TEL 06-6699-8731
FAX 06-6699-8134
Email:teraura@osaka-drc.jp
【会長講演】
座長 窪田昭男(和歌山県立医科大学第2外科学長 特命教授)
「多職種協働で支援するpatient & family-centered care」
【特別講演】
座長 鍋谷まこと(淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院院長)
「Perinatal multidisciplinary for palliative care(周産期における多職種協働による緩和ケアアプローチ)」
Margarita Bidegain MD, MHS-CL (米国Duke大学医学部・小児科准教授)
【シンポジウム】
1、「多職種協働で胎児のいのちをどのように大切に守るか」
Modulator :
和田浩(大阪発達総合療育センター医師)
猿田美雪(淀川キリスト教病院 NICU看護師)
シンポジスト:
宮田郁(大阪医科大学 リエゾン精神看護師)
高橋雄一郎(長良医療センター 産科医師)
武井安津子(愛仁会高槻病院 新生児小児科医師)
佐藤裕美(愛仁会高槻病院 NICU 看護師)
出崎躍(淀川キリスト教病院 臨床心理士)
森喜宣・香奈(大阪医科大学 家族)
柴田兼作(淀川キリスト教病院 家族)
【シンポジウム】
2、「多職種協働で支援するNICUからの地域生活移行」
Modulator :
望月成隆(大阪府立母子保健総合医療センター 新生児科医師)
近藤正子(大阪発達総合療育センター 医療相談室 MSW)
シンポジスト:
祝原賢幸(大阪府立母子保健総合医療センター新生児科医師)
山口真帆(同センター NICU 看護師)
西野千絵(同センター 母性外来看護師)
川野由子(同センター 心理士)
熊清彰(愛染橋病院 小児科医師)
松岡雅一(訪問看護ステーションリハステージ PT)
久保田恵巳(くぼたこどもクリニック 医師)
【ワールドカフェ(事例から学ぶ)】
Facilitator :
杉原康子(大阪発達総合療育センター 臨床心理士)
川野由子(大阪府立母子保健総合医療センター 臨床心理士)
吉田まち子(同センター 看護師)
脇田菜摘(済生会吹田病院 心理士)
出崎躍(淀川キリスト教病院 臨床心理士)
小寺智子(高槻病院 臨床心理士)
2017/1/26
看護師向けアドバンストグリーフサポーター資格取得コースを実施しました。

アドバンスコースは、基礎級(6日)・上級(6日)を修了後に受講していただけます。
日程は2日間。
今回は6名の方が、福岡県や埼玉県など遠方から参加されました。
講師は、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学 学長)と関谷共未先生(大阪あべのカウンセリングルーム代表)です。
様々な概念を踏まえ援助的コミュニケーションについて理解し、アサーションや自己覚知についても学びます。講義の最後には小論文を書き、自らと向き合う時間を設けています。
受講後の感想を紹介します。
【鈴木先生】
・危機モデル、エンリッチメントといった今まで知識のなかった内容を学習できました。特にエンリッチメントは介護の分野から始まったと学び、日々の介護の中で行っているケアをエンリッチメントに繋げて皆と共有していけるよう活用していきたいです。
・在宅療法に移行する際の支援方法を理解できていなかったので、先生から訪問看護師が求めるニードや現場の話を聞くこともでき、今後に活かそうと思いました。家族適応の二重ABCXモデルをもっと深く学び、家族が感じるストレスに対処していきたいと思います。
・家族ケアについての適応モデルを知りアセスメントの手がかりができた。事例からだとじっくり気づくことができるので、実例を記録におこして振り返ることも大切だと思いました。
【関谷先生】
・アサーションのチェックが新しい自分を見つけたように思えた。時々自分でやってみたいと思いました。わかりやすく話してくださりディスカッションもたくさんできたのでとても満足しています。自分ががんばっていたことを皆さん認めて下さって、それがかなりの喜びとなることが予想以上でした。
・自分が負い目に思っていた事も、他の人から+に見られた事の嬉しさや、自らの思いを伝えることの大切さについて、気づかされた授業でした。
・アサーション度チェックリストでは日々自分があまりストレスを抱えていないことに気付くことができました。この研修前だともっと違う結果が出たと思います。セルフケアやディタッチメントのチェックシートなど自分自身を知る上で、とても参考になりました。職場でも紹介したいと思います。
参加していただいた皆様、お疲れ様でした。
次回は3月23日(木)・24日(金)の予定です。

アドバンスコースは、基礎級(6日)・上級(6日)を修了後に受講していただけます。
日程は2日間。
今回は6名の方が、福岡県や埼玉県など遠方から参加されました。
講師は、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学 学長)と関谷共未先生(大阪あべのカウンセリングルーム代表)です。
様々な概念を踏まえ援助的コミュニケーションについて理解し、アサーションや自己覚知についても学びます。講義の最後には小論文を書き、自らと向き合う時間を設けています。
受講後の感想を紹介します。
【鈴木先生】
・危機モデル、エンリッチメントといった今まで知識のなかった内容を学習できました。特にエンリッチメントは介護の分野から始まったと学び、日々の介護の中で行っているケアをエンリッチメントに繋げて皆と共有していけるよう活用していきたいです。
・在宅療法に移行する際の支援方法を理解できていなかったので、先生から訪問看護師が求めるニードや現場の話を聞くこともでき、今後に活かそうと思いました。家族適応の二重ABCXモデルをもっと深く学び、家族が感じるストレスに対処していきたいと思います。
・家族ケアについての適応モデルを知りアセスメントの手がかりができた。事例からだとじっくり気づくことができるので、実例を記録におこして振り返ることも大切だと思いました。
【関谷先生】
・アサーションのチェックが新しい自分を見つけたように思えた。時々自分でやってみたいと思いました。わかりやすく話してくださりディスカッションもたくさんできたのでとても満足しています。自分ががんばっていたことを皆さん認めて下さって、それがかなりの喜びとなることが予想以上でした。
・自分が負い目に思っていた事も、他の人から+に見られた事の嬉しさや、自らの思いを伝えることの大切さについて、気づかされた授業でした。
・アサーション度チェックリストでは日々自分があまりストレスを抱えていないことに気付くことができました。この研修前だともっと違う結果が出たと思います。セルフケアやディタッチメントのチェックシートなど自分自身を知る上で、とても参考になりました。職場でも紹介したいと思います。
参加していただいた皆様、お疲れ様でした。
次回は3月23日(木)・24日(金)の予定です。