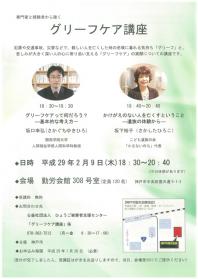- ホーム
- 協会からのお知らせ
協会からのお知らせ
2017/1/5
第8回グリーフ&ビリーブメントカンファレンスのご案内

今年もどうぞよろしくお願い致します。
本日は、第8回グリーフ&ビリーブメントカンファレンスをご案内します。
■日時 2016年2月4日(土)10:00〜16:00(受付10:30〜)
■場所 龍谷大学大阪梅田キャンパス
大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウェストオフィスタワー14階
■アクセス
http://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_osaka.html
*例年と会場が異なりますので、ご注意下さい。
■対象
遺族支援に携わる専門職や医療関係者、関心のある学生
■参加費
2000円(学生無料)
■お申し込み
不要
■主催
日本ホスピス緩和ケア研究振興財団、グリーフ&ビリーブメント研究会
■問い合わせ
グリーフ&ビリーブメント研究会事務局
griefandbereavementconf@gmail.com
■当日のプログラム
9時30分〜 受付開始
10時 開始 挨拶
10時10分〜 講演「患者が経験する同病者の死とその反応」
演者 大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科教授)
座長 石田真弓(埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科助教)
12時30分〜 講演「長期悲嘆に影響を与えている直後のケアのあり方〜当事者の視点
より〜」
演者:本郷由美子(大阪教育大附属池田小学校事件被害者遺族、精神対話士)
座長:黒川 雅代子(龍谷大学短期大学部 准教授)
14時10分〜 講演「薬害HIV遺族のピアサポート」
演者:鈴木葉子(滋賀県HIV派遣カウンセラー、臨床心理士)
座長:村上典子(神戸赤十字病院 心療内科部長)
16時 終了
ご興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。
pdfダウンロード

今年もどうぞよろしくお願い致します。
本日は、第8回グリーフ&ビリーブメントカンファレンスをご案内します。
■日時 2016年2月4日(土)10:00〜16:00(受付10:30〜)
■場所 龍谷大学大阪梅田キャンパス
大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウェストオフィスタワー14階
■アクセス
http://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_osaka.html
*例年と会場が異なりますので、ご注意下さい。
■対象
遺族支援に携わる専門職や医療関係者、関心のある学生
■参加費
2000円(学生無料)
■お申し込み
不要
■主催
日本ホスピス緩和ケア研究振興財団、グリーフ&ビリーブメント研究会
■問い合わせ
グリーフ&ビリーブメント研究会事務局
griefandbereavementconf@gmail.com
■当日のプログラム
9時30分〜 受付開始
10時 開始 挨拶
10時10分〜 講演「患者が経験する同病者の死とその反応」
演者 大西秀樹(埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科教授)
座長 石田真弓(埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科助教)
12時30分〜 講演「長期悲嘆に影響を与えている直後のケアのあり方〜当事者の視点
より〜」
演者:本郷由美子(大阪教育大附属池田小学校事件被害者遺族、精神対話士)
座長:黒川 雅代子(龍谷大学短期大学部 准教授)
14時10分〜 講演「薬害HIV遺族のピアサポート」
演者:鈴木葉子(滋賀県HIV派遣カウンセラー、臨床心理士)
座長:村上典子(神戸赤十字病院 心療内科部長)
16時 終了
ご興味のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。
pdfダウンロード
2016/12/22
年末年始営業について

平成28年12月29日(木)〜平成29年1月4日(水)の期間、お休みをいただきます。
今年もあとわずかとなりました。
皆様にはお世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。

平成28年12月29日(木)〜平成29年1月4日(水)の期間、お休みをいただきます。
今年もあとわずかとなりました。
皆様にはお世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
2016/12/22
2016/12/6
2016年度・第7回公開講座が「在宅における緩和ケア〜がんと非がん〜」のテーマで開催されました。

12月4日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。
講師は岡本双美子先生です。岡本先生は大阪府立大学大学院 看護学研究科 家族看護学 准教授としてご活躍されています。
現在、「在宅終末期がん患者を看取る家族のグリーフケアに関する看護師の教育プログラムの開発」や 「終末期がん患者とその家族への在宅療養移行における支援内容とその評価」、 「小学生を含む地域住民への看取りに関する写真展と講演会を通した死生観の育成への効果」などの研究に取り組まれています。
受講生のご感想をご紹介します。
○興味のある内容でありすぐに仕事でも活かせる内容だった。グリーフケア、子どもへのケア、エンゼルケアなど病棟で困ることも多いのでスタッフと知識共有したい。
○非がんの方への緩和ケアの基本がわかりました。もっとそれぞれの持つ疾患についても考えながらケアしていきたい。グリーフケアの実際についてスタッフに話をし、事例検討会をしたい。
○緩和ケアについて初めから学ぶことができて良かった。予期悲嘆についてのケアや、家族ケアは今後学んだことを実践していきたい。
○緩和ケア、非がん患者へのケアが十分でないが、非がん患者の事を求められる事が多くあるので、職場で啓発活動を行いたい。
今回も参加いただいた受講生の皆様、岡本先生、ありがとうございました。

12月4日(日)当協会で、第7回公開講座を実施しました。
講師は岡本双美子先生です。岡本先生は大阪府立大学大学院 看護学研究科 家族看護学 准教授としてご活躍されています。
現在、「在宅終末期がん患者を看取る家族のグリーフケアに関する看護師の教育プログラムの開発」や 「終末期がん患者とその家族への在宅療養移行における支援内容とその評価」、 「小学生を含む地域住民への看取りに関する写真展と講演会を通した死生観の育成への効果」などの研究に取り組まれています。
受講生のご感想をご紹介します。
○興味のある内容でありすぐに仕事でも活かせる内容だった。グリーフケア、子どもへのケア、エンゼルケアなど病棟で困ることも多いのでスタッフと知識共有したい。
○非がんの方への緩和ケアの基本がわかりました。もっとそれぞれの持つ疾患についても考えながらケアしていきたい。グリーフケアの実際についてスタッフに話をし、事例検討会をしたい。
○緩和ケアについて初めから学ぶことができて良かった。予期悲嘆についてのケアや、家族ケアは今後学んだことを実践していきたい。
○緩和ケア、非がん患者へのケアが十分でないが、非がん患者の事を求められる事が多くあるので、職場で啓発活動を行いたい。
今回も参加いただいた受講生の皆様、岡本先生、ありがとうございました。
2016/11/28
2016年度・第2回公開セミナー「グリーフを小さくするための事前ケア」のテーマで開催されました。

11月27日(日)知恩院和順会館で、第2回公開セミナーを実施しました。
講師は沼野尚美先生です。沼野先生は、チャプレン・カウンセラーとして今まで9つのホスピスで勤務し3000以上の方々の生と死に関わってこられました。
死亡という形でケースが終わった後、遺族にグリーフケアを提供することは、臨床現場では難しいことも多いです。
今回は講義テーマに基づき、やがて訪れる大切な人の死とグリーフに対してできるだけ良く作用するような、事前の心得やコミュニケーションのとり方、家族ケアについてお話いただきました。
受講生のご感想をご紹介します。
○いろんな患者、家族のお話が聞けたことが良かった。テンポの良いお話、先生の観点や感性を感じることができてとても心に響きました。アドバイスも生々しく、現場に沿ったものだったのでこれからすぐに活かせそうなものばかりでした。本当に素晴らしい講義でした。
○実際の患者・家族の声が聞こえるかのようなお話でとても心に入ってきました。Nsの声掛け、コミュニケーションが大切だと思いました。本当に充実した講義でした。
○在宅でも同じ様に本人・家族の生活・暮らしを支える日々の中で悩み、落ち込み、困惑する事が多く、また現場では一人であることも負担となります。しかし本日のお話で思考がとても整理できました。
○グリーフケアは死別後にするものと思っていました。亡くなる前にもできることがたくさんあることを学んで、看取りのケアに活かしていきたいと思います。常に学習が必要だと感じました。
○終末期における患者家族への対応や考え方についてしっかりと知ることができた。
また、スタッフへのグリーフケアも大事である事がわかり、今後の自分のケアやスタッフへの対応について活かせると思いました。クリティカルケア領域でのグリーフケアや家族ケアについても学んでみたい。
○ご家族への説明の重要性が良くわかった。高齢者施設で、家族自身が「もう年だから」と言いながら、安定していた高齢者に体調の変化があったり、急に逝くことがあると受け止めきれていないことがある。大切に思っているからこそホームに預けておられるので、十分な事前説明が必要だと感じた。
参加いただいた受講生の皆様、講師の沼野先生、ありがとうございました。

11月27日(日)知恩院和順会館で、第2回公開セミナーを実施しました。
講師は沼野尚美先生です。沼野先生は、チャプレン・カウンセラーとして今まで9つのホスピスで勤務し3000以上の方々の生と死に関わってこられました。
死亡という形でケースが終わった後、遺族にグリーフケアを提供することは、臨床現場では難しいことも多いです。
今回は講義テーマに基づき、やがて訪れる大切な人の死とグリーフに対してできるだけ良く作用するような、事前の心得やコミュニケーションのとり方、家族ケアについてお話いただきました。
受講生のご感想をご紹介します。
○いろんな患者、家族のお話が聞けたことが良かった。テンポの良いお話、先生の観点や感性を感じることができてとても心に響きました。アドバイスも生々しく、現場に沿ったものだったのでこれからすぐに活かせそうなものばかりでした。本当に素晴らしい講義でした。
○実際の患者・家族の声が聞こえるかのようなお話でとても心に入ってきました。Nsの声掛け、コミュニケーションが大切だと思いました。本当に充実した講義でした。
○在宅でも同じ様に本人・家族の生活・暮らしを支える日々の中で悩み、落ち込み、困惑する事が多く、また現場では一人であることも負担となります。しかし本日のお話で思考がとても整理できました。
○グリーフケアは死別後にするものと思っていました。亡くなる前にもできることがたくさんあることを学んで、看取りのケアに活かしていきたいと思います。常に学習が必要だと感じました。
○終末期における患者家族への対応や考え方についてしっかりと知ることができた。
また、スタッフへのグリーフケアも大事である事がわかり、今後の自分のケアやスタッフへの対応について活かせると思いました。クリティカルケア領域でのグリーフケアや家族ケアについても学んでみたい。
○ご家族への説明の重要性が良くわかった。高齢者施設で、家族自身が「もう年だから」と言いながら、安定していた高齢者に体調の変化があったり、急に逝くことがあると受け止めきれていないことがある。大切に思っているからこそホームに預けておられるので、十分な事前説明が必要だと感じた。
参加いただいた受講生の皆様、講師の沼野先生、ありがとうございました。
2016/11/1
第1回 介護・福祉従事者コース中級が修了しました。

介護・福祉従事者コース中級は4日間。
講師は、大学教授(心理学)、遺族会代表、カウンセラー、緩和ケア医師の4名です。
講義は患者の死別前後を問わず、患者本人と家族が持つグリーフに対してどのように関わるのかをテーマにしています。
グリーフケアは個別性が高いものです。
また、グリーフケアを意識することで専門職自身が共感疲労を持つこともあります。
答えがないと終わりにせず話し合うこと、そして専門職自身の感情を受け止め合うことも大切です。
そのため当協会は少人数制を採用しています。
受講生の皆さまが経験した、介護・福祉の現場で起こったケースを話し合い、ご自身の気持ちや感情と向き合える時間になればと考えています。
受講生のご感想(沈沢欣恵先生講義時)をご紹介します。
○抽象的な概念もスライドや映画、ドラマ、書籍からの引用と紹介など用いておられ分かりやすかったです。またナラティブアプローチについても分かりやすく大変勉強になりました。デスカンファレンスや看取りについて情報共有やお互いの経験を、否定せずに語り合うことはグリーフケアの理解に大変有効だと思います。
○自分の経験を書くこと、伝えることで気持ちが変わることを学びました。
○ちょうどよいスピードの講義で、受講生方々の話も色々聞けてよかった。職場で研修を行う際にも、死について自分自身のことに併せて考えてみるなど、いつもの決まりきった研修内容とは違う内容で研修ができると思う。
○回数を重ねる事で、それぞれの先生が言われた重複している部分の理解が深まり、違うニュアンスや気づき、そういう考え方もあると引き出しが増え、進化しているように感じた。分かりやすい言葉で伝えて下さり、質問しやすい環境だったため、講義中も置き去りにならなかった。個人や文化によって違いはあるが、利用者が亡くなる前からお話する時間を少しでもとれるようにしていきたいと思った。施設でも共有したいと思う。
第1回 介護・福祉従事者コース上級は1月16日からスタートします。
上級は合計6日間。
今後増える「認知症」と「がん」に焦点を当てて、患者と家族のグリーフを考えられるようにしています。
講師は臨床経験豊富な医師の方々に加え、当事者の視点も大切に考え、認知症家族の会の方にもご登壇していただきます。
それではまた。

介護・福祉従事者コース中級は4日間。
講師は、大学教授(心理学)、遺族会代表、カウンセラー、緩和ケア医師の4名です。
講義は患者の死別前後を問わず、患者本人と家族が持つグリーフに対してどのように関わるのかをテーマにしています。
グリーフケアは個別性が高いものです。
また、グリーフケアを意識することで専門職自身が共感疲労を持つこともあります。
答えがないと終わりにせず話し合うこと、そして専門職自身の感情を受け止め合うことも大切です。
そのため当協会は少人数制を採用しています。
受講生の皆さまが経験した、介護・福祉の現場で起こったケースを話し合い、ご自身の気持ちや感情と向き合える時間になればと考えています。
受講生のご感想(沈沢欣恵先生講義時)をご紹介します。
○抽象的な概念もスライドや映画、ドラマ、書籍からの引用と紹介など用いておられ分かりやすかったです。またナラティブアプローチについても分かりやすく大変勉強になりました。デスカンファレンスや看取りについて情報共有やお互いの経験を、否定せずに語り合うことはグリーフケアの理解に大変有効だと思います。
○自分の経験を書くこと、伝えることで気持ちが変わることを学びました。
○ちょうどよいスピードの講義で、受講生方々の話も色々聞けてよかった。職場で研修を行う際にも、死について自分自身のことに併せて考えてみるなど、いつもの決まりきった研修内容とは違う内容で研修ができると思う。
○回数を重ねる事で、それぞれの先生が言われた重複している部分の理解が深まり、違うニュアンスや気づき、そういう考え方もあると引き出しが増え、進化しているように感じた。分かりやすい言葉で伝えて下さり、質問しやすい環境だったため、講義中も置き去りにならなかった。個人や文化によって違いはあるが、利用者が亡くなる前からお話する時間を少しでもとれるようにしていきたいと思った。施設でも共有したいと思う。
第1回 介護・福祉従事者コース上級は1月16日からスタートします。
上級は合計6日間。
今後増える「認知症」と「がん」に焦点を当てて、患者と家族のグリーフを考えられるようにしています。
講師は臨床経験豊富な医師の方々に加え、当事者の視点も大切に考え、認知症家族の会の方にもご登壇していただきます。
それではまた。
2016/10/25
2016年度・第6回公開講座が「医療スタッフが行う遺族会の進め方・グリーフケアのためのプログラム」のテーマで開催されました。

10月23日(日)当協会で、第6回公開講座を実施しました。
講師は坂下裕子さんです。坂下さんは長女を亡くしたことをきっかけに、病気や不慮の事故で子どもを亡くした遺族の会を立ち上げ、 死別・悲嘆・遺族にまつわるテーマと向き合われています。
今回の講座は、テーマに基づいて、遺族会を実施する上で出てくる難しいケースの紹介や、実際に自分がグリーフワークを行うワークショップを体験できる内容でした。
受講生のご感想をご紹介します。
○わかちあいの運営のケースを実際に考えて、参加者全員の意見を聞くことができ、自分の中で考えることができた。自分にはない視点を知ることができて良かった。グリーフワークの木に葉やりんごを貼っていくものを実際にやってみてディスカッションすると思っていた以上に皆さんの思いを理解できた。病棟内で勉強会を実施予定なので、今回学んだことをフィードバックしたいと思う。わかちあいの運営のケース1〜4は病棟メンバーでディスカッションできると思った。グリーフワークの木もメンバーに紹介したいと思う。
○事例を用いてという点が良かった。ただ傾聴する、復誓する技法はあまり使わない、同じ話が出てきたら止める勇気、どんな亡くなり方をした人であっても命の重さは同じ!とても勉強になりました。りんごと葉っぱのワークを通して、もう何年も前に亡くなった祖母の死を、いまだに昨日の事のように鮮明に心に残っている自分に気づきました。
○わかちあいの進行役として事例をもとに考えられたのが、実際自分が行うときにどの目線で行うかイメージすることができました。グリーフワークを実際に行うワークを通して、体験的に学べてすごく良かったです。職場でも遺族会をやっていますが、まずスタッフ全員にグリーフケアについて周知していくことが長くグリーフケアを行っていくために必要だと思いました。プログラムも踏まえて進行やワークを考えな
いといけないと思いました。
○グリーフケアの中身を少しかもしれないが、体験できたように思います。他の方達の意見も聞けて良かったです。職場が病棟でないため24時間経過を看させていただくことはできないですが、看取りの場所を在宅か病院か家族に選択してもらう時、学んだ事を活用できそうです。
今回も遠方から参加いただいた受講生の皆様、講師の坂下さん、ありがとうございました。

10月23日(日)当協会で、第6回公開講座を実施しました。
講師は坂下裕子さんです。坂下さんは長女を亡くしたことをきっかけに、病気や不慮の事故で子どもを亡くした遺族の会を立ち上げ、 死別・悲嘆・遺族にまつわるテーマと向き合われています。
今回の講座は、テーマに基づいて、遺族会を実施する上で出てくる難しいケースの紹介や、実際に自分がグリーフワークを行うワークショップを体験できる内容でした。
受講生のご感想をご紹介します。
○わかちあいの運営のケースを実際に考えて、参加者全員の意見を聞くことができ、自分の中で考えることができた。自分にはない視点を知ることができて良かった。グリーフワークの木に葉やりんごを貼っていくものを実際にやってみてディスカッションすると思っていた以上に皆さんの思いを理解できた。病棟内で勉強会を実施予定なので、今回学んだことをフィードバックしたいと思う。わかちあいの運営のケース1〜4は病棟メンバーでディスカッションできると思った。グリーフワークの木もメンバーに紹介したいと思う。
○事例を用いてという点が良かった。ただ傾聴する、復誓する技法はあまり使わない、同じ話が出てきたら止める勇気、どんな亡くなり方をした人であっても命の重さは同じ!とても勉強になりました。りんごと葉っぱのワークを通して、もう何年も前に亡くなった祖母の死を、いまだに昨日の事のように鮮明に心に残っている自分に気づきました。
○わかちあいの進行役として事例をもとに考えられたのが、実際自分が行うときにどの目線で行うかイメージすることができました。グリーフワークを実際に行うワークを通して、体験的に学べてすごく良かったです。職場でも遺族会をやっていますが、まずスタッフ全員にグリーフケアについて周知していくことが長くグリーフケアを行っていくために必要だと思いました。プログラムも踏まえて進行やワークを考えな
いといけないと思いました。
○グリーフケアの中身を少しかもしれないが、体験できたように思います。他の方達の意見も聞けて良かったです。職場が病棟でないため24時間経過を看させていただくことはできないですが、看取りの場所を在宅か病院か家族に選択してもらう時、学んだ事を活用できそうです。
今回も遠方から参加いただいた受講生の皆様、講師の坂下さん、ありがとうございました。
2016/10/11
看護師・助産師コース アドバンストグリーフサポーター資格取得コースのお知らせ

この度、看護師・助産師コース アドバンスコースに新たな講師を迎えました。
今まで講師を務めていただいた奥野茂代先生(長野県看護大学 名誉教授/ご専門:老年看護学)のご退官に伴い、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学 学長/ご専門:がん看護学・家族看護学)を新たにお迎えしご登壇いただきます。
アドバンスコースは、全2日間。
基礎級、上級を終えた方々が受講して頂けます。
2日間を通して、現場での実践力を高めることができます。また、グリーフケアを考える上で重要である「自分自身を見つめる」時間としていただけます。
スケジュール・概要は以下のページをご参照下さい。
■アドバンストグリーフサポーター資格取得コース
https://www.kyoto-griefcare.or.jp/school_k/schedule_lcs.html
■鈴木志津枝先生 ご経歴
https://www.kyoto-griefcare.or.jp/teacher/koushi_31.html

この度、看護師・助産師コース アドバンスコースに新たな講師を迎えました。
今まで講師を務めていただいた奥野茂代先生(長野県看護大学 名誉教授/ご専門:老年看護学)のご退官に伴い、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学 学長/ご専門:がん看護学・家族看護学)を新たにお迎えしご登壇いただきます。
アドバンスコースは、全2日間。
基礎級、上級を終えた方々が受講して頂けます。
2日間を通して、現場での実践力を高めることができます。また、グリーフケアを考える上で重要である「自分自身を見つめる」時間としていただけます。
スケジュール・概要は以下のページをご参照下さい。
■アドバンストグリーフサポーター資格取得コース
https://www.kyoto-griefcare.or.jp/school_k/schedule_lcs.html
■鈴木志津枝先生 ご経歴
https://www.kyoto-griefcare.or.jp/teacher/koushi_31.html
2016/10/10
第2回グリーフケアシンポジウムを開催しました。

10月2日(日)10:30〜16:30、第2回グリーフケアシンポジウムを京都大学芝蘭会館で開催しました。今回は3部構成です。(第1部 基調講演・第2部 パネリスト講演・第3部 パネルディスカッション)
テーマは、グリーフケアとしての終末期ケア。患者が亡くなる前に得る家族の経験は、遺族となった後、それぞれのグリーフワークに影響します。看護師・介護福祉従事者・緩和ケアチームなどの医療従事者・医師など、それぞれが関わることのできるタイミングと専門性を活かしながら患者、家族、遺族の主体性をどのように大切にするのかを考えるシンポジウムとなりました。また他者へのケアを考えるあまり後回しにされがちな、セルフケアの重要性についても話し合われました。
第1部 基調講演は、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学学長/日本看護系大学協議会理事/日本がん看護学会代議員など)をお招きしご講演いただきました。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・グリーフケアとしてエンリッチメントがいかに有効であるかが良く理解できました。また、エンリッチメントについて具体的でわかりやすく、介護付有料老人ホームにおいて積極的に取り組もうと考えました。今まではあまり家族を巻き込まないようにしていました。
・グリーフケアそのものの理解が深まり、今後の関わり方の方針が明確になった。講演の進め方や口調などとても聞きやすく、時間が経つのも忘れていました。
・療養病棟に勤め、看取りの方が多い。今後今日の講義を役立てていけたらと思っています。今後最も必要なケアだと認識しました。
・終末期患者・家族に対するgoodpracticeとなるケアの患者と家族の充実した時間を持てるような支援をどうすれば良いか普段どういう働きかけがポイントになるかよくわかった。
第2部はパネリストによる講演でした。4名に各20分ずつお話いただきました。パネリストは、船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副院長/日本未熟児新生児学会監事/日本小児科学会近畿地区代議員)・白山宏人先生(医療法人拓海会大阪北ホームケアクリニック院長)・岡本双美子先生(大阪府立大学大学院 看護学研究科 家族看護学 准教授)・坂下裕子先生(子ども遺族の会 小さないのち 代表)です。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・具体的なお話でした。小児の経験も長く、焦点をあてて考えていただいているのが
嬉しいです。白山先生の在宅での看取りがイメージできました。エンドオブライフケ
アは病院でも繋がることだと思います。坂下さんのお話はナースの支えにもなること
でした。
・ポイントがぐっと絞られていたので分かりやすかった。
・船戸先生の亡くなった子を正面玄関から見送るという思いに感動しました。白山先生の患者ととことん寄り添う。岡本先生の家族の一員である子どもへのケア。坂下先生のお母様への思い。ご自身の辛い闘病生活。Nsに同調し傷ついた家族など、学びになったことが沢山ありました。
・医療者としての在り方というか、プロとしてどう患者と家族に関わっていけば良いのか自分の中で初めて知ることが多すぎて、色々な立場の方の意見が聞けて勉強になりました。
・家族の手記を見たり、グリーフケア(家族看護)、遺族の体験談を改めて聞いて、職場での出来事(普段の看護)を振り返りながら講演を聞けたので面白かった。明日からのケア、サポートに繋がると思えました。
第3部は パネルディスカッションは司会を足利学先生(藍野大学 医療保健学部 作業療法学科 教授/臨床心理士)にお願いし、先ほどのパネリスト方と実施しました。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・テーマの患者の主体性をどう支えるか、支援する側のコンディションの調整についてとても勉強になりました。どれも確実な答えはないですが、ヒントになることは確かでした。支援することばかり考えすぎている自分がいて、自分のことをあまりしっかり見つめていないことに気付かされました。今日のシンポジウム初めての参加でしたが、とても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。
・主体性・セルフケア、どちらもなんとなくわかっていてもどうしたらいいかわからないことが多いのが現状だった。色々な先生も多方面からの意見が聞けたのは貴重だった。
・主体性を支える、意思決定支援を支えるために何をしたらいいのかがわかった。また、セルフケアについても自分のグリーフケアが出来ていない時もあるので、自分の今の状態を認めてリフレッシュできるようにしていきたいと思いました。
・自分のグリーフケアについても学べて参考になった。看護師には「何かしてあげたい」という本能がある生物だと聞き、少し気持ちが楽になった。意思決定について学べた。
今回も多くの方に参加いただきました。
お越しいただいた皆様、シンポジストの皆様、ありがとうございました。

10月2日(日)10:30〜16:30、第2回グリーフケアシンポジウムを京都大学芝蘭会館で開催しました。今回は3部構成です。(第1部 基調講演・第2部 パネリスト講演・第3部 パネルディスカッション)
テーマは、グリーフケアとしての終末期ケア。患者が亡くなる前に得る家族の経験は、遺族となった後、それぞれのグリーフワークに影響します。看護師・介護福祉従事者・緩和ケアチームなどの医療従事者・医師など、それぞれが関わることのできるタイミングと専門性を活かしながら患者、家族、遺族の主体性をどのように大切にするのかを考えるシンポジウムとなりました。また他者へのケアを考えるあまり後回しにされがちな、セルフケアの重要性についても話し合われました。
第1部 基調講演は、鈴木志津枝先生(神戸市看護大学学長/日本看護系大学協議会理事/日本がん看護学会代議員など)をお招きしご講演いただきました。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・グリーフケアとしてエンリッチメントがいかに有効であるかが良く理解できました。また、エンリッチメントについて具体的でわかりやすく、介護付有料老人ホームにおいて積極的に取り組もうと考えました。今まではあまり家族を巻き込まないようにしていました。
・グリーフケアそのものの理解が深まり、今後の関わり方の方針が明確になった。講演の進め方や口調などとても聞きやすく、時間が経つのも忘れていました。
・療養病棟に勤め、看取りの方が多い。今後今日の講義を役立てていけたらと思っています。今後最も必要なケアだと認識しました。
・終末期患者・家族に対するgoodpracticeとなるケアの患者と家族の充実した時間を持てるような支援をどうすれば良いか普段どういう働きかけがポイントになるかよくわかった。
第2部はパネリストによる講演でした。4名に各20分ずつお話いただきました。パネリストは、船戸正久先生(大阪発達総合療育センター副院長/日本未熟児新生児学会監事/日本小児科学会近畿地区代議員)・白山宏人先生(医療法人拓海会大阪北ホームケアクリニック院長)・岡本双美子先生(大阪府立大学大学院 看護学研究科 家族看護学 准教授)・坂下裕子先生(子ども遺族の会 小さないのち 代表)です。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・具体的なお話でした。小児の経験も長く、焦点をあてて考えていただいているのが
嬉しいです。白山先生の在宅での看取りがイメージできました。エンドオブライフケ
アは病院でも繋がることだと思います。坂下さんのお話はナースの支えにもなること
でした。
・ポイントがぐっと絞られていたので分かりやすかった。
・船戸先生の亡くなった子を正面玄関から見送るという思いに感動しました。白山先生の患者ととことん寄り添う。岡本先生の家族の一員である子どもへのケア。坂下先生のお母様への思い。ご自身の辛い闘病生活。Nsに同調し傷ついた家族など、学びになったことが沢山ありました。
・医療者としての在り方というか、プロとしてどう患者と家族に関わっていけば良いのか自分の中で初めて知ることが多すぎて、色々な立場の方の意見が聞けて勉強になりました。
・家族の手記を見たり、グリーフケア(家族看護)、遺族の体験談を改めて聞いて、職場での出来事(普段の看護)を振り返りながら講演を聞けたので面白かった。明日からのケア、サポートに繋がると思えました。
第3部は パネルディスカッションは司会を足利学先生(藍野大学 医療保健学部 作業療法学科 教授/臨床心理士)にお願いし、先ほどのパネリスト方と実施しました。
いただいた感想の一部をご紹介します。
・テーマの患者の主体性をどう支えるか、支援する側のコンディションの調整についてとても勉強になりました。どれも確実な答えはないですが、ヒントになることは確かでした。支援することばかり考えすぎている自分がいて、自分のことをあまりしっかり見つめていないことに気付かされました。今日のシンポジウム初めての参加でしたが、とても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。
・主体性・セルフケア、どちらもなんとなくわかっていてもどうしたらいいかわからないことが多いのが現状だった。色々な先生も多方面からの意見が聞けたのは貴重だった。
・主体性を支える、意思決定支援を支えるために何をしたらいいのかがわかった。また、セルフケアについても自分のグリーフケアが出来ていない時もあるので、自分の今の状態を認めてリフレッシュできるようにしていきたいと思いました。
・自分のグリーフケアについても学べて参考になった。看護師には「何かしてあげたい」という本能がある生物だと聞き、少し気持ちが楽になった。意思決定について学べた。
今回も多くの方に参加いただきました。
お越しいただいた皆様、シンポジストの皆様、ありがとうございました。
2016/8/30
2016年度・第4回公開講座が「症例検討の実際〜看護職のグリーフケアに焦点をあてて」のテーマで開催されました。

8月28日(日)当協会で、第4回公開講座を実施しました。
講師は玉木敦子先生です。玉木先生は現在、神戸女子大学看護学部看護学科教授としてご活躍されています。
女性のメンタルヘルス、周産期メンタルヘルス、ストレスマネジメントをテーマに研究や実践活動をされています。
受講生のご感想をご紹介します。
○自身のこれまでの振り返りができた。またかつてもっと何か出来たのではないかと悩んでいたことに対して、職場では、私だったらそんなことはなく、うまくできたはずと言われる方がいた。看護師としての自分のスキルがないのでは…と思い始めていた。しかし、今回同じ様に思っている方が居て、心が穏やかになった。職場の他のスタッフとも共有したいと思った。申し送りの後のカンファレンスで、今日学んだことを活用していきたいと思う。
○日々、時間に追われ考えることを忘れていた「当たり前」に気付くことができました。様々な場で働く人達からの言葉や意見に学び、考える機会となり、参加して本当に良かったです。
ファシリテーターの役割は、カンファレンスだけでなく職場のスタッフ一人ひとりとの関わりに活用できそうです。患者・家族のための、そして看護師のためのカンファレンスを見直していきたいです。
とてもいい環境の中で学ぶことができました。
○患者・家族へのグリーフケアは中心的に行われるが、看護職に関してはなかなかできずにいた。カンファレンスのあり方、持ち方一つで変わることもあるということがわかった。自分がファシリテーターとしてカンファレンスや場の雰囲気を作っていきたい。
○本日の講座の目的がはっきりしていたので、事例検討の内容だけでなく運営方法やファシリテーターの役割等、今後に役立つ内容でした。デスカンファレンスを繰り返すことで担当者(事例提供者)もその他のスタッフも学ぶ事ができると思います。
○他施設の看護師や事例検討ができ良かった。自分が日頃行っているファシリテーターのあり方を振り返ることもできた。倫理カンファ、デスカンファ、事例の振り返り等行う機会があるので、事例検討の進め方について参考になる機会だった。今回初めて参加させていただいたが、少人数で、非常に丁寧な学習の機会を提供していただき、ありがとうございました。
皆様、非常に満足されてお帰りになりました。
今回も遠方から参加いただいた受講生の皆様、玉木先生、ありがとうございました。

8月28日(日)当協会で、第4回公開講座を実施しました。
講師は玉木敦子先生です。玉木先生は現在、神戸女子大学看護学部看護学科教授としてご活躍されています。
女性のメンタルヘルス、周産期メンタルヘルス、ストレスマネジメントをテーマに研究や実践活動をされています。
受講生のご感想をご紹介します。
○自身のこれまでの振り返りができた。またかつてもっと何か出来たのではないかと悩んでいたことに対して、職場では、私だったらそんなことはなく、うまくできたはずと言われる方がいた。看護師としての自分のスキルがないのでは…と思い始めていた。しかし、今回同じ様に思っている方が居て、心が穏やかになった。職場の他のスタッフとも共有したいと思った。申し送りの後のカンファレンスで、今日学んだことを活用していきたいと思う。
○日々、時間に追われ考えることを忘れていた「当たり前」に気付くことができました。様々な場で働く人達からの言葉や意見に学び、考える機会となり、参加して本当に良かったです。
ファシリテーターの役割は、カンファレンスだけでなく職場のスタッフ一人ひとりとの関わりに活用できそうです。患者・家族のための、そして看護師のためのカンファレンスを見直していきたいです。
とてもいい環境の中で学ぶことができました。
○患者・家族へのグリーフケアは中心的に行われるが、看護職に関してはなかなかできずにいた。カンファレンスのあり方、持ち方一つで変わることもあるということがわかった。自分がファシリテーターとしてカンファレンスや場の雰囲気を作っていきたい。
○本日の講座の目的がはっきりしていたので、事例検討の内容だけでなく運営方法やファシリテーターの役割等、今後に役立つ内容でした。デスカンファレンスを繰り返すことで担当者(事例提供者)もその他のスタッフも学ぶ事ができると思います。
○他施設の看護師や事例検討ができ良かった。自分が日頃行っているファシリテーターのあり方を振り返ることもできた。倫理カンファ、デスカンファ、事例の振り返り等行う機会があるので、事例検討の進め方について参考になる機会だった。今回初めて参加させていただいたが、少人数で、非常に丁寧な学習の機会を提供していただき、ありがとうございました。
皆様、非常に満足されてお帰りになりました。
今回も遠方から参加いただいた受講生の皆様、玉木先生、ありがとうございました。