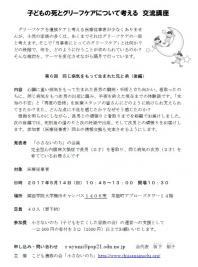- ホーム
- 協会からのお知らせ
協会からのお知らせ
2017/6/20
不在のお知らせ

第22回日本緩和医療学会学術集会・フューネラルビジネスフェア2017出展のため、6月22日(木)〜6月27日(火)の期間、事務局不在の日が多くなります。
場合により対応が遅れたり、連絡がつきづらくなります。
申し訳ございませんが、何卒ご理解とご容赦をいただけましたら幸いです。
6月28日(水)以降は通常通り、営業致します。
お急ぎの方は、お問い合わせページよりお問い合わせ下さい。

第22回日本緩和医療学会学術集会・フューネラルビジネスフェア2017出展のため、6月22日(木)〜6月27日(火)の期間、事務局不在の日が多くなります。
場合により対応が遅れたり、連絡がつきづらくなります。
申し訳ございませんが、何卒ご理解とご容赦をいただけましたら幸いです。
6月28日(水)以降は通常通り、営業致します。
お急ぎの方は、お問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
2017/6/19
第15回日本小児がん看護学会 学術大会のお知らせ

この度は、表題の学術集会をご紹介します。
会期 2017年11月9日(木)〜11日(土)
会場 ひめぎんホール
愛媛県民文化会館
〒790-0843 愛媛県松山市道後町2-5-1
大会長 薬師神裕子(愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 小児発達看護学)
参加費 医師15,000円 看護師10,000円 医師・看護師以外5,000円 学部学生無料
大会プログラムは、以下URLをご参照下さい。
■第15回日本小児がん看護学会学術集会HP
http://www.c-linkage.co.jp/jspho-jspon2017/
■日本小児がん看護学会HP
http://www.jspon.com/
(※第59回日本小児血液・がん学会学術集会、第22回がんの子どもを守る会公開シンポジウムと合同開催です。)
今回の学術集会のプログラムでは、子どもと家族の癒しや笑顔を与える団体の方にもご参加いただき、施設や会の活動をご紹介いただくプログラムも設けておられます。
また、日本小児がん看護学会の教育委員会主催のプログラムで、「小児看護におけるEnd of Life Care」というセミナーも開催予定です。
ご興味のある方は、いかれてみてはいかがでしょうか。
PDFダウンロード

この度は、表題の学術集会をご紹介します。
会期 2017年11月9日(木)〜11日(土)
会場 ひめぎんホール
愛媛県民文化会館
〒790-0843 愛媛県松山市道後町2-5-1
大会長 薬師神裕子(愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 小児発達看護学)
参加費 医師15,000円 看護師10,000円 医師・看護師以外5,000円 学部学生無料
大会プログラムは、以下URLをご参照下さい。
■第15回日本小児がん看護学会学術集会HP
http://www.c-linkage.co.jp/jspho-jspon2017/
■日本小児がん看護学会HP
http://www.jspon.com/
(※第59回日本小児血液・がん学会学術集会、第22回がんの子どもを守る会公開シンポジウムと合同開催です。)
今回の学術集会のプログラムでは、子どもと家族の癒しや笑顔を与える団体の方にもご参加いただき、施設や会の活動をご紹介いただくプログラムも設けておられます。
また、日本小児がん看護学会の教育委員会主催のプログラムで、「小児看護におけるEnd of Life Care」というセミナーも開催予定です。
ご興味のある方は、いかれてみてはいかがでしょうか。
PDFダウンロード
2017/6/13
6月11日(日)に2017年度第2回公開講座を開催いたしました。

講師は、当協会の講師でもあり、こども遺族の会「小さないのち」代表の坂下裕子さんです。
「産科・NICUで深い悲しみを支えるかかわり」をテーマに、そのかかわりについて、実際の体験者の声や文献をもとに受講生の皆さまと一緒に考えました。
また、ワークショップとして実際に産着を作成して頂きました。
言葉を越えての寄り添いを感じて頂けたのではないかと思います。
以下、受講生のアンケートを紹介します。
○何か言葉を言わないといけないと思っていたが、必ずしも言葉が必要ではないということが良くわかりました。
スタッフ間で話し合う機会となると思います。
○体験された方の思いや声がよくわかって良かった。
今はボランティアの方がつくってくれたベビー服をきせてあげているが、死産の処理中は時間があるので、そういう時に一緒に服を作ってあげたりしながら思い出作りをしていきたいと思った。
○自分の考えて言葉にならなかった思い(母側)が理解でき、自分の感情は正常だということに気付けました。死産となったお母さん、お父さんに最期、家族とどう過ごしたいかを今日勉強したことをもとに、選択肢を提供していきたいです。
自分の病院に持ち帰り、知識を広めていきたいと思います。
○寄り添うだけでもよい。言葉は必要ないこともあるということを知った。病棟でのグリーフケアの改善点などが明確になった。
お忙しい中、お越し頂きました受講生の皆さま、講師の坂下さんありがとうございました。

講師は、当協会の講師でもあり、こども遺族の会「小さないのち」代表の坂下裕子さんです。
「産科・NICUで深い悲しみを支えるかかわり」をテーマに、そのかかわりについて、実際の体験者の声や文献をもとに受講生の皆さまと一緒に考えました。
また、ワークショップとして実際に産着を作成して頂きました。
言葉を越えての寄り添いを感じて頂けたのではないかと思います。
以下、受講生のアンケートを紹介します。
○何か言葉を言わないといけないと思っていたが、必ずしも言葉が必要ではないということが良くわかりました。
スタッフ間で話し合う機会となると思います。
○体験された方の思いや声がよくわかって良かった。
今はボランティアの方がつくってくれたベビー服をきせてあげているが、死産の処理中は時間があるので、そういう時に一緒に服を作ってあげたりしながら思い出作りをしていきたいと思った。
○自分の考えて言葉にならなかった思い(母側)が理解でき、自分の感情は正常だということに気付けました。死産となったお母さん、お父さんに最期、家族とどう過ごしたいかを今日勉強したことをもとに、選択肢を提供していきたいです。
自分の病院に持ち帰り、知識を広めていきたいと思います。
○寄り添うだけでもよい。言葉は必要ないこともあるということを知った。病棟でのグリーフケアの改善点などが明確になった。
お忙しい中、お越し頂きました受講生の皆さま、講師の坂下さんありがとうございました。
2017/6/12
第8回 複雑性悲嘆(CG)研修会のお知らせ

表題の研修会をご紹介します。
ご興味のある方は、以下URLより直接お申込み下さい。
認知症介護者のグリーフにご興味のある方は、行かれてみてはいかがでしょうか。
■概要■
本研修会は、複雑性悲嘆やそのリスクの高い人たちへの専門的なケアや治療について、検討や意見交換を行う場として、平成22年に立ち上がりました。
今年で8回目になります。
第8回CG研修会では、家族療法をベースとしたPauline Boss博士の「あいまいな喪失(AL)」理論と介入方法を取り上げます。
そして、あいまいな喪失の1つである認知症患者家族の事例に対し、博士から事前にコンサルテーションを受け、それをもとに参加者全員でディスカッションを行います。
Boss博士の家族をみる視点は、さまざまな喪失の支援、複雑性悲嘆の支援を考える上で、多くの示唆に富んでいます。
詳細は研修会URLをご覧下さい。宜しければ、今回も是非ご参加下さい。
■日時 平成29年8月26日(土曜日)午前11時〜午後5時
■場所 大阪 関西学院大学梅田キャンパス
■研修費 5,000円
■定員 先着50名
■内容
第1部 講演
「あいまいな喪失による悲嘆の複雑化を防ぐために:その家族へのアプローチ」
甲南女子大学 瀬藤乃理子
第2部
「事例検討会:認知症患者の家族への支援」
コンサルタント: Pauline Boss博士
司会: 石井千賀子先生(TELLカウンセリング)
1)尊敬する夫が高度認知症となり、在宅介護が難しくなった家族の事例
2)レビー小体型認知症の妻を看取った夫とその家族の事例
■研修会URL
http://gandb.net/researchgroup/pg128.html
■申し込み
FAX、メール、申し込みフォームから受付いたします。
申し込みフォーム(PCのみ)
https://www.secure-cloud.jp/sf/1495967556JhKkDZjt
■主催 甲南女子大学 瀬藤研究室
■協力
グリーフ&ビリーブメント研究会
JDGS(日本災害グリーフサポート)プロジェクト
PDF ダウンロード

表題の研修会をご紹介します。
ご興味のある方は、以下URLより直接お申込み下さい。
認知症介護者のグリーフにご興味のある方は、行かれてみてはいかがでしょうか。
■概要■
本研修会は、複雑性悲嘆やそのリスクの高い人たちへの専門的なケアや治療について、検討や意見交換を行う場として、平成22年に立ち上がりました。
今年で8回目になります。
第8回CG研修会では、家族療法をベースとしたPauline Boss博士の「あいまいな喪失(AL)」理論と介入方法を取り上げます。
そして、あいまいな喪失の1つである認知症患者家族の事例に対し、博士から事前にコンサルテーションを受け、それをもとに参加者全員でディスカッションを行います。
Boss博士の家族をみる視点は、さまざまな喪失の支援、複雑性悲嘆の支援を考える上で、多くの示唆に富んでいます。
詳細は研修会URLをご覧下さい。宜しければ、今回も是非ご参加下さい。
■日時 平成29年8月26日(土曜日)午前11時〜午後5時
■場所 大阪 関西学院大学梅田キャンパス
■研修費 5,000円
■定員 先着50名
■内容
第1部 講演
「あいまいな喪失による悲嘆の複雑化を防ぐために:その家族へのアプローチ」
甲南女子大学 瀬藤乃理子
第2部
「事例検討会:認知症患者の家族への支援」
コンサルタント: Pauline Boss博士
司会: 石井千賀子先生(TELLカウンセリング)
1)尊敬する夫が高度認知症となり、在宅介護が難しくなった家族の事例
2)レビー小体型認知症の妻を看取った夫とその家族の事例
■研修会URL
http://gandb.net/researchgroup/pg128.html
■申し込み
FAX、メール、申し込みフォームから受付いたします。
申し込みフォーム(PCのみ)
https://www.secure-cloud.jp/sf/1495967556JhKkDZjt
■主催 甲南女子大学 瀬藤研究室
■協力
グリーフ&ビリーブメント研究会
JDGS(日本災害グリーフサポート)プロジェクト
PDF ダウンロード
2017/5/31
第2回「子どものグリーフサポート実践者研修会」のご案内

表題の研修会をご紹介します。
日時:平成29年6月24日(土)
第1部 10:00〜12:00 第2部 13:00〜17:00
開場:あしなが心塾レインボーハウス (東京都日野市百草892-1)
定員:50名
研修費:4,000円(おひとり・昼食付き)
対象:子供のグリーフサポートを実践(計画)している団体・個人
講師:西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所長)
シンシアホワイト先生(Kids Hurt Too Hawaii 創設者)
お申込み期日;平成29年6月16日
主催:高橋聡美研究室 NPO法人子どもグリーフサポートステーション
共催:あしなが育英会
●お申込み、その他概要は、添付のチラシをご参照の上、直接お申込みください。
ダウンロードhttp://kyoto-griefcare.or.jp/strage/20170531.pdf

表題の研修会をご紹介します。
日時:平成29年6月24日(土)
第1部 10:00〜12:00 第2部 13:00〜17:00
開場:あしなが心塾レインボーハウス (東京都日野市百草892-1)
定員:50名
研修費:4,000円(おひとり・昼食付き)
対象:子供のグリーフサポートを実践(計画)している団体・個人
講師:西田正弘先生(あしなが育英会東北事務所長)
シンシアホワイト先生(Kids Hurt Too Hawaii 創設者)
お申込み期日;平成29年6月16日
主催:高橋聡美研究室 NPO法人子どもグリーフサポートステーション
共催:あしなが育英会
●お申込み、その他概要は、添付のチラシをご参照の上、直接お申込みください。
ダウンロード
2017/5/29
2017年度・第1回公開講座が「子供の死の理解とグリーフケア−子どもにとっての死別とは−」のテーマで開催されました。

5月28日(日)当協会で、第1回公開講座を実施しました。
講師は茎津智子先生です。
茎津先生は現在、京都光華女子大学 健康科学部看護学科 教授として教育に携わっておられます。ご専門は、小児看護学です。
約10年前より、死別による子どもの悲嘆、喪失の問題に関心をもち、子どもの死別による喪失の認識など親、教員、看護職への実態調査などを行うと同時に、子どもの悲嘆・喪失について医療職、教員への啓発活動を行ってこられました。
受講生のご感想をご紹介します。
○自分が勉強したかったこと、疑問に思っていたことが内容に盛り込まれていました。今年度、きょうだいのグリーフについてどうやっていこうか悩んでいたが、方向が見えました。病棟内で共有し、きょうだいのグリーフケアについて何らか可視化できる活動に繋げられそうです。
○子どもへの介入は実際、それほど多くなく、子の発達段階による死の理解など知らない内容ばかりでした。病棟内でスタッフに向けて勉強会を開催、また看護研究に活
かしていきたいと思います。
○子どもにとっての死別とは、年代によって理解度は違うがわかりやすく伝えることの大切さや、子どもと向き合うことの大切さを知る事ができ、今まで接してきたお子
さんに公開する場面があることに気付かされた。今後は学んだことを活かしていきたいと思います。振り返りを行うこともでき、自分自身を見つめ直す機会にもなりまし
た。本日学んだことは、スタッフと情報共有して子どもさんへの関わり、サポートについて皆が関心をもってケアを考えるよう努めていきたい。
○子どもの認知の過程については知っていたが、死をどうとらえるのか、ということについては詳しく知れた。また幼児だけではなく、思春期の子供にも焦点をあてる必
要も学んだ。今回学んだ内容に加えて、さらに学習していきたいと思います。
○子どもの喪失がおとなの喪失と基本的には同じであることを理解できた。子どもの想いや体験をおとなが決めつけたり、思いこんだりしてはいけないと感じた。勉強し
た内容を「親を亡くした子供を支える、おとなへのケア」に活かしていきたいと思う。
なお、今年度は10月29日(日)に、小島ひで子先生(小児看護学)による公開セミナー「終末期患者を親に持つ子どもへのグリーフケア」も予定しております。
ご興味のある方はご検討ください。
本日も遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の茎津先生、お疲れ様でした。

5月28日(日)当協会で、第1回公開講座を実施しました。
講師は茎津智子先生です。
茎津先生は現在、京都光華女子大学 健康科学部看護学科 教授として教育に携わっておられます。ご専門は、小児看護学です。
約10年前より、死別による子どもの悲嘆、喪失の問題に関心をもち、子どもの死別による喪失の認識など親、教員、看護職への実態調査などを行うと同時に、子どもの悲嘆・喪失について医療職、教員への啓発活動を行ってこられました。
受講生のご感想をご紹介します。
○自分が勉強したかったこと、疑問に思っていたことが内容に盛り込まれていました。今年度、きょうだいのグリーフについてどうやっていこうか悩んでいたが、方向が見えました。病棟内で共有し、きょうだいのグリーフケアについて何らか可視化できる活動に繋げられそうです。
○子どもへの介入は実際、それほど多くなく、子の発達段階による死の理解など知らない内容ばかりでした。病棟内でスタッフに向けて勉強会を開催、また看護研究に活
かしていきたいと思います。
○子どもにとっての死別とは、年代によって理解度は違うがわかりやすく伝えることの大切さや、子どもと向き合うことの大切さを知る事ができ、今まで接してきたお子
さんに公開する場面があることに気付かされた。今後は学んだことを活かしていきたいと思います。振り返りを行うこともでき、自分自身を見つめ直す機会にもなりまし
た。本日学んだことは、スタッフと情報共有して子どもさんへの関わり、サポートについて皆が関心をもってケアを考えるよう努めていきたい。
○子どもの認知の過程については知っていたが、死をどうとらえるのか、ということについては詳しく知れた。また幼児だけではなく、思春期の子供にも焦点をあてる必
要も学んだ。今回学んだ内容に加えて、さらに学習していきたいと思います。
○子どもの喪失がおとなの喪失と基本的には同じであることを理解できた。子どもの想いや体験をおとなが決めつけたり、思いこんだりしてはいけないと感じた。勉強し
た内容を「親を亡くした子供を支える、おとなへのケア」に活かしていきたいと思う。
なお、今年度は10月29日(日)に、小島ひで子先生(小児看護学)による公開セミナー「終末期患者を親に持つ子どもへのグリーフケア」も予定しております。
ご興味のある方はご検討ください。
本日も遠くから来ていただいた受講生の皆様、講師の茎津先生、お疲れ様でした。
2017/5/24
葬儀従事者コース中級 宿原先生の講義を行いました。

この春、葬儀従事者コース中級は、より現場での遺族対応を考えられる内容にリニューアルしました。
本日は、リニューアル後、初となる宿原寿美子先生(株式会社キュア・エッセンス代表取締役)による講義が行われました。
宿原先生は、大手アパレル・化粧品などの流通業界を経験後、葬儀業全般に携わり、セレモニー専門学校のフューネラルディレクターコース・エンバーミングコースの講師として活躍してこられました。
現在は学生・企業にて処置やメイクを指導する傍ら、葬祭の現場で自ら処置やメイクを実践されています。
また、葬祭業界だけでなく、グリーフケアの観点から、医療・介護現場へエンゼルケアのあり方なども提唱されています。
受講生は、静岡・長野・愛知・岐阜など様々な場所からお越しで、ロールプレイやディスカッションも熱心に取り組まれていました。
また、休憩時間も、葬儀の現場で経験した様々な事例が話し合われ、熱気に包まれた講義でした。
受講者の感想をご紹介します。
■ご納棺、死化粧からこんなに深くグリーフケアについて学ばせていただいたことに感謝します。それにしましても、人としての基本=思いやりである事、改めて基本を教えていただきました。また自分自身に向き合うこと、逃げずに自身と向き合い自身
を愛せるように努めます。その日感じたことを一か月間書き込んだり、事例から読み取ることを始めていこうと思います。
■葬祭ディレクターとしても納棺士としても現役の方が講師で現場での様子がとても勉強になりました。ありがとうございました。グリーフケアの深さ、そして怖さを痛切に感じますが頑張っていきたいです。お顔の保湿クリームを活用するなど、すぐに
でも現場でやりたいと思いました。
■現場での経験を基に、講義をいただいたのでわかりやすい内容で、かつグリーフケアについて振り返る良い機会でした。ワーク中心の講義で、他参加者の方々の意見も聞けたことが参考になりました。死化粧を中心としてグリーフケアを再考していきた
いです。
■湯かんは業者任せになっていたので、今日お話を聞けることを楽しみにしていました。葬儀とは違い湯かんから伝わるグリーフの話を伺えてよかったです。私の話も聴いて下さり嬉しかったです。途中、内容が難しく感じたところもありましたが、「思
いやり」の大切さを理解しました。まずは今日ノートを一冊購入し、自分を知るためにがんばっていこうと思います。
参加された皆様、宿原先生ありがとうございました。

この春、葬儀従事者コース中級は、より現場での遺族対応を考えられる内容にリニューアルしました。
本日は、リニューアル後、初となる宿原寿美子先生(株式会社キュア・エッセンス代表取締役)による講義が行われました。
宿原先生は、大手アパレル・化粧品などの流通業界を経験後、葬儀業全般に携わり、セレモニー専門学校のフューネラルディレクターコース・エンバーミングコースの講師として活躍してこられました。
現在は学生・企業にて処置やメイクを指導する傍ら、葬祭の現場で自ら処置やメイクを実践されています。
また、葬祭業界だけでなく、グリーフケアの観点から、医療・介護現場へエンゼルケアのあり方なども提唱されています。
受講生は、静岡・長野・愛知・岐阜など様々な場所からお越しで、ロールプレイやディスカッションも熱心に取り組まれていました。
また、休憩時間も、葬儀の現場で経験した様々な事例が話し合われ、熱気に包まれた講義でした。
受講者の感想をご紹介します。
■ご納棺、死化粧からこんなに深くグリーフケアについて学ばせていただいたことに感謝します。それにしましても、人としての基本=思いやりである事、改めて基本を教えていただきました。また自分自身に向き合うこと、逃げずに自身と向き合い自身
を愛せるように努めます。その日感じたことを一か月間書き込んだり、事例から読み取ることを始めていこうと思います。
■葬祭ディレクターとしても納棺士としても現役の方が講師で現場での様子がとても勉強になりました。ありがとうございました。グリーフケアの深さ、そして怖さを痛切に感じますが頑張っていきたいです。お顔の保湿クリームを活用するなど、すぐに
でも現場でやりたいと思いました。
■現場での経験を基に、講義をいただいたのでわかりやすい内容で、かつグリーフケアについて振り返る良い機会でした。ワーク中心の講義で、他参加者の方々の意見も聞けたことが参考になりました。死化粧を中心としてグリーフケアを再考していきた
いです。
■湯かんは業者任せになっていたので、今日お話を聞けることを楽しみにしていました。葬儀とは違い湯かんから伝わるグリーフの話を伺えてよかったです。私の話も聴いて下さり嬉しかったです。途中、内容が難しく感じたところもありましたが、「思
いやり」の大切さを理解しました。まずは今日ノートを一冊購入し、自分を知るためにがんばっていこうと思います。
参加された皆様、宿原先生ありがとうございました。
2017/5/16
公開講座を追加しました。

公開講座についてお知らせします。
第2回公開講座「産科・NICUで深い悲しみを支えるかかわり」ですが、早々に定員に達しました。
そこで、別の日程 10月1日(日)で設定致しました。
ワークショップを行うため、少人数限定としています。
すでに残席わずかとなっております。
ご興味のある方は、お早めにお申込み下さい。
■追加回 公開講座
http://www.kyoto-griefcare.or.jp/seminar/schedule.php#seminar-13

公開講座についてお知らせします。
第2回公開講座「産科・NICUで深い悲しみを支えるかかわり」ですが、早々に定員に達しました。
そこで、別の日程 10月1日(日)で設定致しました。
ワークショップを行うため、少人数限定としています。
すでに残席わずかとなっております。
ご興味のある方は、お早めにお申込み下さい。
■追加回 公開講座
http://www.kyoto-griefcare.or.jp/seminar/schedule.php#seminar-13
2017/4/10
2017/4/6
子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座(5月)のお知らせ

医療従事者向けグリーフケア講座をご案内致します。
主催はこども遺族の会「小さないのち」です。
当協会開設当初よりご支援いただいている坂下裕子さんが会長をつとめられています。
ご興味のある方は以下、ご参照ください。
●子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座●
グリーフケアを遺族ケアと考える医療従事者が少なくありませんが、小児の家族の多くは、あくまでそれはグリーフケアの一部だと考えます。
そこで「当事者にとってのグリーフケア」とは何か?どの段階で、何を、どのように行うことが求められているのか?
そんな検討を、テーマを変化させながら隔月で行っています。
第6回 同じ病気をもって生まれた兄と弟(後編)
■内容
心臓に重い病気をもって生まれた長男の闘病・手術と立ち向かい、看取ったのちに、同じ病気をもつ次男の出産に臨み、手術を終えた現在までの体験談です。
「未知の不安」と「再度の恐怖」を医療スタッフの皆さんにどのように助けられ支えられてきたか?また、どんな点に不足を感じたか?なぜそう感じたのか?
根拠を明らかにしながら、長男との頑張りと看取りまでを前編でお届けしました。
次の後編では、死別後の道のりと次の妊娠や出産、そして次男との頑張りをお届けします。参加者(医療従事者)同士の情報交換も充実させるようにします。
■発表者
「小さないのち」の会員
完全型心内膜床欠損症で長男(0才)を看取り、同じ病気の次男(2才)を育てているお母さんです。
■対象
医療従事者
■日時
2017年5月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30
■場所
関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階
■定員
40人(要予約)
■参加費
小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として一口500円の寄付を3口(1500円)以上でお願いいたします。
■申し込み・問い合わせ
s-ayumi@pop21.odn.ne.jp
会代表 坂下(さかした) 裕子(ひろこ)
■主催
こども遺族の会「小さないのち」http://www.chiisanainochi.org/

医療従事者向けグリーフケア講座をご案内致します。
主催はこども遺族の会「小さないのち」です。
当協会開設当初よりご支援いただいている坂下裕子さんが会長をつとめられています。
ご興味のある方は以下、ご参照ください。
●子どもの死とグリーフケアについて考える 交流講座●
グリーフケアを遺族ケアと考える医療従事者が少なくありませんが、小児の家族の多くは、あくまでそれはグリーフケアの一部だと考えます。
そこで「当事者にとってのグリーフケア」とは何か?どの段階で、何を、どのように行うことが求められているのか?
そんな検討を、テーマを変化させながら隔月で行っています。
第6回 同じ病気をもって生まれた兄と弟(後編)
■内容
心臓に重い病気をもって生まれた長男の闘病・手術と立ち向かい、看取ったのちに、同じ病気をもつ次男の出産に臨み、手術を終えた現在までの体験談です。
「未知の不安」と「再度の恐怖」を医療スタッフの皆さんにどのように助けられ支えられてきたか?また、どんな点に不足を感じたか?なぜそう感じたのか?
根拠を明らかにしながら、長男との頑張りと看取りまでを前編でお届けしました。
次の後編では、死別後の道のりと次の妊娠や出産、そして次男との頑張りをお届けします。参加者(医療従事者)同士の情報交換も充実させるようにします。
■発表者
「小さないのち」の会員
完全型心内膜床欠損症で長男(0才)を看取り、同じ病気の次男(2才)を育てているお母さんです。
■対象
医療従事者
■日時
2017年5月14日(日)10:45〜13:00 開場10:30
■場所
関西学院大学梅田キャンバス1406室 茶屋町アプローズタワー14階
■定員
40人(要予約)
■参加費
小さないのち(子どもを亡くした家族の会)の運営への支援として一口500円の寄付を3口(1500円)以上でお願いいたします。
■申し込み・問い合わせ
s-ayumi@pop21.odn.ne.jp
会代表 坂下(さかした) 裕子(ひろこ)
■主催
こども遺族の会「小さないのち」http://www.chiisanainochi.org/